4月といえば山菜採りシーズン到来。一面真っ白だった山も少しずつ緑が見られるようになってきた。
今時期、山に入れば様々な美味しい山菜たちと出会うことが出来る。
そんな中でも今回は、北海道の定番である山菜「行者にんにく」の採り方をご紹介していこうと思う。
行者にんにくとは
実際の採り方をご紹介する前に”行者ニンニク”の簡単な特徴をご紹介。


~行者ニンニクについて~
・ネギ属・行者ニンニク
・大きさ20cmから30cmの多年草
・葉の大きさは3cmから10cmほど
・別名:キトピロ・アイヌネギ・ヤマビル・ヤマニンニク
行者にんにくとは、ネギ属の多年草。




分布は 南は奈良県から北は北海道で見られるものの、東北より南では高山にしか生えていない。
よって主に採取できるのは東北・北海道に限られるだろう。
また、食べられるまで育つのに7~8年と非常に時間がかかる実は希少な植物である。
行者ニンニクの名前の由来
この不思議な名前の由来は諸説があるが、山ごもりをして厳しい修行をしていた行者が食べていたことからつけられた説が有名だ。
また、行者が食べると滋養が付きすぎるので禁止になったという説もあるらしい。
行者ニンニクの食べ方
強いニンニク臭が特徴で、調理法は醤油漬けやおひたし、天ぷらなど。
また北海道名物のジンギスカンと一緒に焼いて食べるとものすごく美味しい。
その希少さと風味豊かな味から、春の味覚として通販などで1キロ5千円で取引されている。
地域によっては栽培物も行われており、こちらは天然物よりも少し早く出回り始める。
行者ニンニク採りの注意点(間違えやすい毒草)
そんな魅力たっぷりの行者ニンニクだが、一点気をつけなければならない事がある。
それは同じ時期、同じ時期に生えている毒草と間違えやすいことだ。
代表的な植物がバイケイソウやイヌサフラン、スズラン。






画像の植物はバイケイソウ。行者ニンニクと全く同じ環境に生えている有毒植物。
そしてこれらの毒草はやっかいなことに行者ニンニクと見た目が似ており、素人目には判断がつきにくい。
なお直近だと2016年の4月23日に旭川市で行者ニンニクとイヌサフランを間違えて男性が死亡する事故が発生している。
絶対に毒草と間違えないためにも、不安で慣れないうちは・・・
2、怪しいと思ったら手持ち出来るポケットタイプの図鑑やネットで葉を見比べる。
3、前日に調べて特徴を把握しておく
これらのことを徹底しよう。少しでも不安だと思ったら採らないことが大切だ。
行者ニンニクの見分け方
それでは実際に、写真を解説しながら行者ニンニクの見分け方を紹介していく。


これが本物の行者ニンニクの全体写真。
では次の項目で他の毒草とは違う点について解説していこう。
1.根際が網目状の繊維で覆われている
行者にんにくは、根際が網目状の繊維で覆われており、茎が赤紫色になっている。



これがその繊維だ。網目状になっている。
もし行者にんにくのような野草を発見したら、まず根本をチェックしてみよう。


スズランを除く他の毒草では編目状の繊維や赤紫色の茎が存在しない。つるっと普通の茎だったらやめておいた方が吉。


網目状の繊維を取った状態。赤色の茎がよく分かるはず。
2.葉や茎をぎゅっと握って臭いをかぐ
次にご紹介する方法がもっとも見分けが簡単だ。
行者にんにくらしき野草の葉や茎をぎゅっと強くつまんで匂いをかいでみてほしい。(葉の場合は手でこすった方が分かりやすいかもしれない)
そうすると、本当に行者ニンニクならニンニク臭がツンとしてくる。
逆にもし無臭なら・・・ほぼ100%別の野草。
必ず採るのを止めよう。
なお、著者も最初はこの方法を使って見分けをしていた。


ちなみに実際に切り取った後も、切り口に鼻を近づけるとニンニク臭が確認可能だ。
ただ・・・スズランは茎が赤い場合も。



天然食材探しへ近くに気軽に出かけよう!(http://blog.livedoor.jp/ogita5/archives/51331107.html)より引用
しかし根元に編目状の繊維がないこと、ニンニク臭がしないこと、スズランは葉が硬くしっかりしているなどの違いがある。
慣れないうちは1,2の方法を両方試して確実に判断することを推奨したい。
行者にんにくの生えやすいポイント
では実際に行者ニンニクの採り方や生えやすいポイントなどを解説。



初心者の方々は恐らく「採ってみたいけど、どこに生えているのか分からない」と悩むことが多いはず。
数年前までは著者もその一人で、ありそうな場所に行ってはなにも見付からず帰ってくることも多かった。
しかし、1度ポイントを見付けてからは、生えていそうな場所が大体分かるように!
つい先日も、道南に住んでから初めて探しに行き、一発で探り当てることに成功した。
行者にんにくの見つけ方~沢を探そう
では筆者が感じた行者にんにくが生えやすいポイントとはどんなところなのか?というと
2、バイケイソウの生えている場所
この2点だ。
1のポイントは写真で説明すると、このような川をまず見つけることから始まる。


基本的に行者ニンニクは、日当たりのよい湿地付近の傾斜に生えていることが多い。
よって川を発見してから探すと見つけやすいのだ。
2.バイケイソウの周りに注目
そして2のポイントであるバイケイソウが生えている場所について。
このバイケイソウはさきほども記載したように行者にんにくと同じような環境に生えている有毒の植物である






なぜこのバイケイソウが生えている場所を探すのかというと・・・
行者にんにくは小さくてわかりにくいが、この植物は春先でも大きいものだと50cm程度あり、遠くからも発見しやすいから。
つまり!似た場所に生えているなら、まず見つけやすいバイケイソウを探してしまおうという作戦だ。
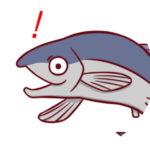
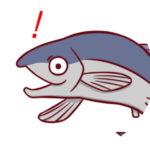
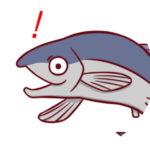



バイケイソウの生えていた場所から、少し奥を探すと本命を発見。奥に見えるのが先ほどの小川
なお、バイケイソウを見つけた後は傾斜を注意深く観察しながら上流へ進んでにんにくを探そう。
以上のポイントをまとめると・・・
2、川の上流へ少しずつ歩き、山肌に行者にんにくのような植物がないか探す。
この方法を使えば、きっとあなたも行者ニンニクに出会うことができるはずだ
行者にんにくの採り方
無事に行者にんにくを見つけたあとは、実際に切り取っていくことになる。
次は行者にんにくの正しい採り方を見ていこう。
といっても、見つけたら摘むのは簡単で、根本をカッターやハサミでちょんと切るだけだ。


根本付近をチョン。
球根を傷つけないように丁寧に行っていこう。
無理な引き抜きはNG
決して無理に引き抜いて株ごと持ち帰るのは止めよう。
行者にんにくは育つまでに多くの年数がかかり、球根から抜き去ってしまうと再生することがなくなってしまう。
次の世代まで楽しめるように守っていただきたい。
行者にんにくを採る際のお願い
行者にんにくは限られた環境にしか生えない希少な植物。
採れるだけたくさん採って帰るようなことは決してせず、
小さな株は残す、食べる分だけ持ち帰る。ことを徹底していただければありがたい。
また、山に入るということはクマやマムシなどの危険生物と出くわす危険性もある。
行く前にしっかりと対策をし、少しでも危険を感じたらその場から離れよう。
まとめ
そんな訳で今回は「行者にんにくの特徴」や「生えているポイントの探し方」「注意点」などを紹介してきた。
このページを見て、行者にんにくの採り方などがおわかりいただけただろうか。
特に注意していただきたい点は有毒植物と間違えないようにすること。
怪しければ絶対に手を出さないようにしよう。


カタクリと一緒に生える行者ニンニク。どちらも希少な植物。
行者にんにく採りは、まるで宝探しのように見つけるところから、実際に採取するまで非常に面白い。
ただ、繁殖力も弱く限られた希少な資源なのも事実。
ルールとマナーを守って、行者にんにく採りを楽しんでいただければ幸いだ。







